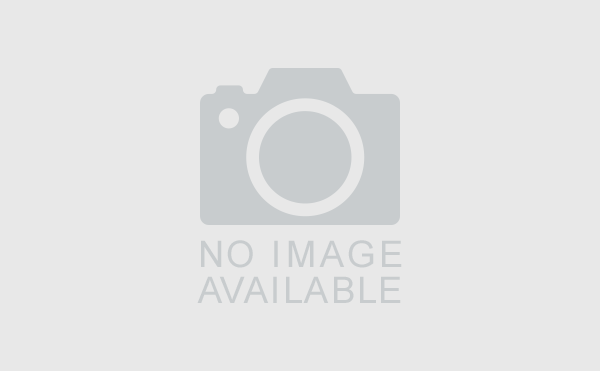4月入学を考える
学年度のスタートは4月のままでよいか?
日本の学年度は4月に始まる。季節が冬から春に変わり、地域によっては桜の咲く中、入学式が行われる。新しい学校・学年の進学・進級する季節としてはマッチしていると感じる人は多いのかも知れない。
学年度の開始を4月から9月に変えてはどうかとの議論が続けられて久しい。しかし、話題にはなるものの国会等しかるべき場所で熱い議論が交わされた記憶はない。唯一思い出せるのは、コロナ禍が始まった直後の2020年3月。 故安倍元首相が全国の教育機関を休校にした際、滅多にないこのチャンスを活かして9月開始の学年度に移行してはとの議論が起こった。
しかし、一定の準備・移行期間を経ず、思いついたかのような変更には、現場が猛反発した。当然である。決めるのは簡単だが、現場での作業は想像を絶するものがあることは、教育に携わってきた人であれば容易に理解できる。
だが再びこの議論が復活したという記憶はまったくない。それでいいのであろうか。9月への移行には目的がある。最も大きな目的は教育の国際化だ。日本の教育に更なる国際化が求められていることは言うまでもない。多くの教育機関が「国際」を謳い文句にするも、実態を伴わないものが多く存在する。今こそ教育の国際化に向けた大改革を進めるべきではないか。
弊社の調査では、北米、ヨーロッパ、北アフリカ、中東諸国、そしてアジアでは中国が9月(一部8月)開始となっている。オセアニアは1~2月、南米は2~3月が一般的だが、圧倒的に9月が多い。なぜ南半球にあるオセアニアや南米は1~3月なのか。9月を採用する国々もそうだが、多くは夏の終わりを新学期としている。暑くて長い夏は学年度の間にもってきているのだ。
学年度の4月から9月に移行する議論には、併せて行わなければならないより大きな課題もある。国をはじめとする行政の様々な制度の見直し、民間においても入社時期の見直しなどなど、並行して行われなければならない。
大きな問題であり一時的な混乱はあるかも知れないが、できない改革ではない。議論は続けなければならない。そしてその議論は、次世代を担う人材の育成である教育の課題を主軸とするものであってほしいと願う。