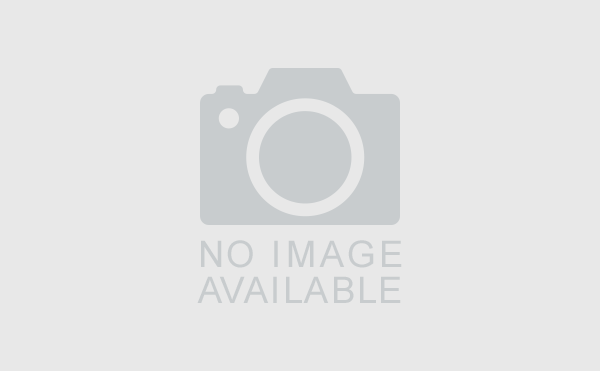日米の教育実習の比較
日本の教育実習制度は今のままで良いか?
日本の学校の教壇に立ち、授業を行うには教員免許の取得が必要なことはいうまでもない。4年制大学に通い教職課程に籍を置く学生には、通常4年次に2~3週間の教育実習を行うことが義務づけられている。実際の教育の現場で、教員に求められる仕事を一通り体験することを目的としている。
大学卒業後、社会人1年生の教員の大半は即クラスを持ち、教壇に立って授業を行う。教員免許を取得する過程で、実務体験を積むことは絶対的に必要なことだ。しかし実務体験を積む期間として、2~3週間というのは充分なのだろうか。
教員の仕事は教科指導だけではない。考査の実施・採点・評価、生活指導、部活動の顧問、進路指導、保護者対応など、業務は多岐にわたる。これらすべてを一度に経験する必要はないかとは思うが、それにしても教員としての仕事を把握するのに、2~3週間というのは充分なのか。
現実問題として、教員を志したものの、大学時に思い描いていた仕事と実際のギャップに嫌気がさし、1~2年で離職してしまう教員が多くいることも事実である。
アメリカの大学で教職課程に籍を置く学生は、州により若干の差はあるものの、通常4年次に1学期間、12~14週間の教育実習を体験することが教職課程を修了すること、つまり教員免許を取得することの条件になっている。実習期間に、日本と大きな違いがある。これは、日米の教育実習に対する基本的な考え方の違いからくるものと判断できる。
教員不足が深刻化している。より多くの大学生が教職を望むようになり、そしてより優秀な教員が現場で活躍するようになるにはどうしたら良いのか。更なる改革が求められている。